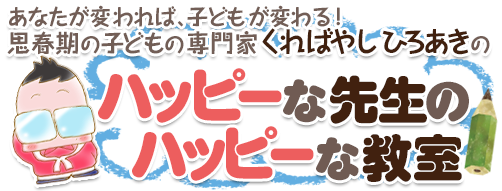わかり合えない人を理解する訓練こそがこの社会を優しくするのかもしれない。

とある資格認定ビジネスの話。
ある講師さんがその協会を離れることになった。
協会が発行する資格の更新料が毎年必要だったそうだ。
自分の力で十分お客さんを集められる彼女は、資格の更新料がもったいないので辞めることにしたのだという。
すると、彼女は活動ができなくなった。
なぜかというと、資格を取得したときに協会と交わした契約書に、辞めたあと1年間はそのコンテンツを用いた活動をしてはならないと書かれていたからだ。
協会を離れたら1年間同じ講座をしてはいけない。
交わした契約書にそういうことが書かれていたのだそうだ。
その話を聞いた妻が、「ちょっと聞いてよ」と言ってきた。
「辞めたら1年間も活動できないんだって。酷くない?」というのである。
「ふーん、そんなルール、あるかなー?」と僕はすぐにGoogle先生に尋ねた。
協会を辞めたら活動できないなんてルールはどこにも存在しなかった。
「そんなの、Googleで出てこないけどね」と返事した。
「それがさ、契約書があって、ハンコ押しちゃったんだって」と彼女。
「なんて書いてあったの?」と尋ねる僕に前述の1年間活動停止の話をした。
それでまた「ひどくない?」と繰り返した。
僕はそれを聞いて「契約書にハンコ捺したなら仕方ないよね」と答えた。
「そうかなぁ?ひどくない?」と彼女。
「ひどいかどうかはわからないけれど契約書にそうやって書いてあるんでしょ?」
「書いてあるけど、そんなの、普通はちゃんと読まないじゃん?」
「でもさ、契約書なんだから読まない方が悪いでしょ?」
「かわいそうだよね」
「かわいそうかもしれないけど、仕方ないじゃん」
「かわいそうだよね」
「かわいそうかもしれないけど、仕方ないじゃん」
「かわいそうだよね」
「かわいそうかもしれないけど、仕方ないじゃん」
互いの正しさが違うので議論が噛み合わない。
こういう夫婦間のやりとりを挙げたらキリがない。
彼女は感情で物事を考える。
僕は論理で物事を考える。
感情の人は「法的に」とか「ルールが」とかよりも「心情的に」で考える。
論理の人は「気持ちはわかるけど」と言いながら「正論」でバッサリ切り捨てる。
「そんな契約をするなんてヒドい!」と考える彼女と、「そんな契約でも押印したんだから仕方がない」と考える僕。
法治国家だから、契約書を交わしたのであれば仕方がないという正論をぶっ飛ばして、「そんなのおかしい!」と憤れるのはすごいことだと思う。
そう考えると、講座受講の前に契約書を交わしているかが重要かもしれない。
講座を受講した後で、後出しでいろいろ出すのは反則なんだろうな。
争点となるのはそのくらいだろうか。
まー、職業選択の自由が憲法で保障されたこの国で、人の営業活動を拘束するのは、よほどしっかり作り込まれた契約書でなければ難しいかもしれないけれど。
まー、それはそれとして。
我が家の夫婦の会話は、噛み合わないなって思うことが多い。
そういうとき、「なぜ噛み合わないか」を考えることが面白い。
先日、雪が降って高速道路が通行止めになった。
お友達のお宅に伺う用事があったので、別ルートで向かうことにした。
ところが帰る頃には雪も溶けて、高速道路の通行止めも解除されていた。
彼女が運転する車の助手席で僕はスマホの道路情報を確認した。
「もう高速道路の通行止めは解除されてるからこのまま高速道路に乗れるよ」と伝えた。
ところが、しばらくして彼女はスマホで情報を調べ出した。
それで僕は「なんかそれって信頼されてないなって感じがするよね」って話をした。
彼女は「そんなことはない。自分でも調べたいだけだ」と言った。
「いや、僕が調べて、高速道路の通行止めが解除されてるって言ってるのを、もう一度自分で調べたら、あー、この人、俺のこと信頼してないなーって思うよね?」と伝えた。
彼女は「いや、そんなことはない」と言った。
んー、今、話してるのは、受け取る側の気持ちを言ってるから、「そんなことはない」と話し手は思っていても、受け手は嫌な気持ちになるよ、って話をしているわけで。
あー、なんて伝わらないんだろう、と思う。
こうやって僕は、ほぼ毎日、伝わらねーな、と思っている。
そして、この伝わらなさをいつか本にできないかと考えている。
この社会には、こんなミスコミュニケーションが山ほどあるはずなのだ。