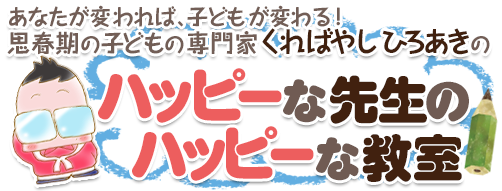承認欲求を満たしてくれる人の存在が自信につながる

「人から認められたい」という気持ち。
これを承認欲求と呼びます。
マイナスのイメージを持つ人も多いだろうけれど、承認欲求があるから僕らは努力できる部分が少なからずあります。
それが原動力となるならば上手に活用したい。
自分は価値のある人間だ。
そうやって周りの人に認めてもらいたい思いは僕にだってあります。
その気持ちがあることは決して恥ずかしいことではないんです。
「何くそ!認めさせてやるぞ!」
そんな気持ちでがんばってこともありましたし。
SNSで発信をすることが当たり前になったZ世代の若者たちにとっては、フォロワー数やいいねなどのリアクションが自分の価値だと錯覚してしまうことがあります。
大人でも「稼ぎ」が自分の価値だったり、「人脈」が自分の価値だったり。
そういう誤解は、承認欲求をどんどん大きくさせてしまいます。
目標に向けての大きなモチベーションとなる承認欲求ですが、歯止めが効かなくなると人間関係を悪くする原因にもなります。
僕らは自分のことを自分で認めるのが苦手です。
隣の芝生は青く見えるもので、「周りはすごい!自分はまだまだ!」という人も多いでしょう。
謙虚さは日本人の魅力でもありますが、どうもそのようなスタンスが日本人全体の自己肯定感の低さにもつながっているような気がしてなりません。
「他者に認められたい」という思いは、自分で自分を認められないと、さらに大きなものになります。
こういうとき、自分のことを認めてくれる人がいると、心が大きく満たされていきます。
僕が学校の先生だったとき。
そう、それはまだ新卒のころでした。
毎月、国語の研究会に参加していました。
僕の入っていた部会は、漢字指導や文法指導などを扱う、本当に人気のない部会でした。
なにせ、ヒラの教員は僕だけ。
他の先生は校長先生や教頭先生ばかりです。
それで毎月、「何か持ってこい」と言われます。
漢字や文法の授業だけでなく、ありとあらゆる資料を「酒の肴」として提供しました。
すると、偉い先生たちが「あーだ、こーだ」と教えてくれるのです。
若い頃の僕は毎日の授業をこなすのが精一杯で、自分のやっていることに価値があるのかなんて考える余裕はありませんでした。
でも、いろんな先生が僕の資料を見て、「これにはこういう価値がある」「ここはこう工夫するともっと良くなる」と教えてくれるのです。
とても勉強になったし、自分のやっていることには価値があるのだと実感することができました。
自分のことを認めてくれる、そんな場所だったのです。
結局文部科学省から上海日本人学校に行くまで、僕はずっと研究会に所属していました。
たくさんのことを学ばせていただいたし、何より自信をつけることができました。
「自信がない」という人は多くいます。
あなたのことを認めてくれる人の存在。
これが自信につながるのではないか。
そんなことを思っています。