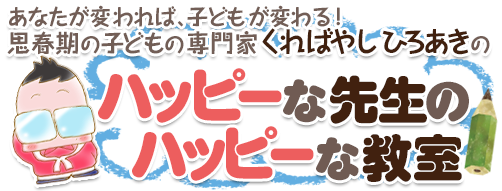結局、どんな力がついたか?ってことなんですよ

学習指導要領には、いつ、どんな力をつけるべきかが描かれている。
基本的には一条校と呼ばれる学校は、学習指導要領に則って行われる。
フリースクールの類いは、そういう拠り所となるようなものは設けていないからフリーなわけだけど。
進学する際には、上級学校側は学習指導要領に記載された内容を当該学年で学んだという前提で入試を行うから、このあたりがフリーだと対応できない子どもたちも現れる。
まー、受験のために教育してるわけじゃねーぞ!と言われたら、あーそうですか、という感じだけど。
基本的にはこの、いつ、どんな力をつけるべきか、に沿って学習活動ってのは行われるわけだ。
この年齢にはこれができててほしいよね、みたいなことがまとめられてる感じ。
で、それに合わせて「教科書」ってのは作られている。
ちゃんとそれに合わせてるか?ってのは、検定されているから検定教科書なのである。
というわけで、一条校では基本的にはこの教科書で教えていく。
何事にも例外があるので、「基本的には」と表現しておく。
もう一度書くが教科書「で」教えていく。
これ大事なこと。
教科書を教えているわけではなく、教科書で教えていく。
だから、時には「教科書にはこう書かれているけれど、実際はちょっと違うよね」なんてこともある。
教科書に「冬は寒い」と書かれていても、「僕らは南半球にいるから逆にあたたかいけどね」みたいなことはあって当然である。
ワシら、オーストラリアに住んでますねん。
冬はあったかいねん!
でも、教科書に寒いって書いてあるから、ホントは今、むっちゃ寒いねん!
…とはならない。
なぜ関西弁なのかはよくわからない。
で、ここからが本題。
学習指導要領に記された「いつ、どんな力をつけるべきか」ってことが1番重要なんだけど、気づけば教科書をすべて教えることに一生懸命になる、なんてことがよく起こる。
本来、教科書が全部終わらなくても、「いつ、どんな力をつけるべきか」が達成されていれば問題はないわけ。
逆に、「いつ、どんな力をつけるべきか」は押さえられてないけれど、教科書は終わってます、は問題なのである。
子どもにどんな力がついたか、ではなく、どこまで教科書が終わったか、を大切にしてしまうところがあるのだな。
結果として、子どもにちゃんと力がついたかどうか、は置いておいて、とにかく先に進んでテスト範囲を終える、みたいなことになりがちである。
まー、業務上致し方ないことで、「アンタ、間違ってるよ!」なんて言うつもりはない。
ひとつの学年を複数の教科担任が授業をしてたりすると、定期テストがあって授業進度を揃えないと苦情の嵐になりますからな。
そんな綺麗事は言ってられなくて、とりあえず教科書を終わらせることに一生懸命にならざるをえないのである。
まー、一斉授業の限界ともいえる。
もっと先へ進めるのに立ち止まらなきゃならない子も生まれるし、よくわかってなくて置いてきぼりになる子も出てくる。
全員取りこぼしなく、個に応じられたら最高だけど、1名で40人を見ている先生からすれば、「それ、無理ゲーっすよ」となっても仕方がない。
そう考えると、もっといろんなことを根本から見直していかなきゃならないんだろうね、と思う。
「教科書で教える」もそうなんだけど、「先生が教える」ってのも、そろそろ考え直さないといけないと思う。
結局、ポイントとしては、ちゃんと生きていくのに必要な力がついたか?ってことになっていくんだろうな。