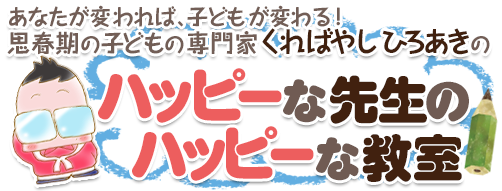「聞く力」の誤解
「聞く」とはどういう意味でしょうか?
ただ黙って聞くことができれば、それは聞く力があると言えるのでしょうか?
人の話をついつい遮ってしまう。
そんな人がいます。
僕もそういう傾向があるので、口を挟まぬように気をつけて、相手の話を最後まで聞くように心がけています。
では、それさえできれば「聞く力」があると言えるかというと、なんだか違う気がするのです。
相手の話を黙って聞いていればいい、という話ではなさそうです。
いろんな人と話をしていると、気持ちよく話せる人と気持ちよく話せない人がいることに気がつきました。
おそらく多くの人はこういうとき、気持ちよく話せる人は気持ちよく、気持ちよく話せない人は不快に感じ、それで終わりなわけですが、僕はそういうとき、「なぜだろう?」と気になってしまうのですね。
それで「気持ちよく話せない人」との会話を楽しんでしまうのです。
なぜ気持ちよく話せないのか、観察してしまいます。
すると、とても大切なことがわかりました。
「気持ちよく話せない人」というのは、聞いていないんです。
本人は「聞く力」があると思っていますが、話している側は「この人、聞いてないな」と感じてしまう。
この感覚をもう少し言語化してみますね。
一度、受け止めるんです。
対話をするときって、自分と同じ意見のときもあれば、異なる意見のときもありますよね。
自分と異なる意見のときに、ちゃんと受け止める器があるか。
この一点で、話している相手の気持ちよさって変わるんです。
ある話し合いの場で、一人の子が調べてきた内容を伝えました。
その会議のリーダーが、「それは気にしなくていい」と言いました。
調べてきた子の顔が曇ったのを僕は見逃しませんでした。
はい、一瞬の出来事です。
こういうの、学校の先生って見逃さないんですよね。
調べてきた子は、調べなきゃよかったな、意見を言わなきゃよかったな、と思っちゃいますよね、心の中で。
はい、じゃあリーダーの自己評価はどうか、というと、ここに誤解が生じます。
調べてきた子が調べてきたことを話している間、黙って最後まで聞いているんです。
だから、私はちゃんと聞いている、ということになります。
聞いたうえで、「それは気にしなくていい」と自分の意見を述べただけだ、と考えます。
ところが、話をした方は「聞いてもらえなかった」と感じます。
ここがポイントなんです。
ただ聞けばいいってものじゃないんですね、聞く力って。
ここで一旦、受け止めてほしいんです。
「こんな懸念材料がありますよ」と、その子は調べてきたんです。
「なるほど、そうなんですね」とまずは受け止めます。
「どんなことが心配ですか?」とか「どんな対策が考えられますか?」と一つ質問を挟むことも有効です。
質問できるのは、相手の言葉に興味や関心を示すことになります。
それは「ちゃんと聞いてますよ」の合図になるのです。
「それは気にしなくていい」のであれば、その理由を伝えてあげるのもいいでしょう。
ただ、この場合は調べてきた内容を事前に把握していて十分な対策が練られているときには有効です。
つまり、「聞く」という一連の行為は、実は話をした側が気持ちよく話を終えられるか、というところまでがセットなんですね。
次も話したいと思うか。
ここが重要なんです。
議論になってもいいんです。
自分の意見が最終的に否決されてもいいんです。
一度受け止めてもらえて、議論のまな板に乗ったならそれで良いのです。
「切り捨てられた感覚」が残ると、話し手は「もう話すまい」と思ってしまうのです。
肯定しなきゃいけない、否定しちゃいけない。
そういうことではないんですよね。
対話するってさ、「それは違うと思うよ」ってときは絶対あるから、それはそれでいいんです。
あ、もちろん「違うよ」とは言いませんよ。
「君はそう言うけどさ、俺はこう思うんだよ」ってことは当然あるさ、という話なんですね。
ただ、そういうとき、ちゃんと一度受け止められるか、なんです。
話している側が「話してよかった」と思えるかどうか。
ここが大事なんです。
「聞く力」って、ただ聞いていればOKではないんです。
「あ、この人は私の話を受け止めてくれたな。耳を傾けてくれる人だな」という実感を相手が持てたかどうか、なんです。
聞く側の器が試される。
特に、自分と異なる意見と出会ったときほど、自分の器が試されます。
話を最後まで聞いていれば聞いたことになるのかというと、そうではないのだ。
このことは十分に押さえておく必要があると僕は考えています。