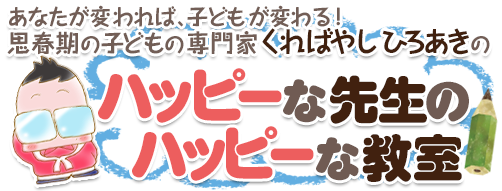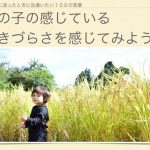括ってしまうと見えなくなるんだ!ー発達障害のお話ー

「ウチの子、発達障害って先生に言われたんですけど、どう思いますか?」
そんなことを尋ねられることがある。
人はカテゴライズしたがるからね。
発達には個体差があって、みんなそれぞれ得意不得意があって、つまりは凸凹しているのが人間だ。
それは、俗に言う「発達障害」と呼ばれる人も、何の問題もなく生きている人も同じで。
全員が多かれ少なかれ凸凹している。
ここは大事なポイントなんだけど、みんな凸凹している。
そういう中で、集団生活に困難を感じるような状況のとき、僕らは生きづらさを感じるわけ。
例えば、他者とうまくコミュニケーションが取れないとか。
うまく感情を制御できなくて人と衝突するとか。
そういうときは、手を差し伸べてあげればいい。
大人の都合で、「あの子は言うことを聞かないから」なんて理由で、「あの子は発達障害です」みたいなことをし出したら、それはとても子どもも保護者も傷つけるし、危険なことだ。
「ウチの子、発達障害って先生に言われたんですけど、どう思いますか?」
そんな言葉を聞くたびに、これは大人の都合だろうか?それとも子どもに寄り添ったうえでの言葉だろうか?と一人考えてしまう。
「指示をしても動かない。
だから、あの子はダメなんだ」
そんなふうに考えるなら、教育者の怠慢だと思う。
伝え方を変えればいいし、支援をすればいい。
向日葵には向日葵の育て方があり、朝顔に朝顔の育て方がある。
だから、「あぁ、この子は朝顔なのだから支柱が必要だな」と思うだけである。
ただ、支柱を立てるだけでは難しいときもある。
保護者も困っている。
本人も困っている。
集団生活の中で生きることに困難を抱えている。
そんなときは、発達検査を促すときもある。
もちろん、保護者や本人とは丁寧なやりとりが必要。
信頼関係がないと、なかなかうまく真意も伝わらない。
だから、慎重に物事を進めていく。
最後の判断は、お医者様がきちんと判断してくれる。
教育者が勝手な判断をすべきものではない。
教育者として支援し、困っているから医療機関につなぐ。
自分たちはジャッジする人ではないのだ。
そういう立ち位置を間違えると、保護者との関係を壊すことになる。
そもそも、そういった判断は微妙なケースが多い。
ADHD、アスペルガー、自閉症、LD、知的障害などなど、いろんな名前をつけられるけれど、単純に「どれかひとつ」というわけではなく、人それぞれいろんなものが混ざり合っている。
そして、それぞれには軽重、グラデーションがある。
ファッションショーの仕事で、ダウン症の子どもたちの面談を何度かしたことがある。
よく知られたことだが、ダウン症の子どもたちって顔立ちが似ている。
でも、話をしてみると、中身は当然違っていて、かなり凸凹があるのだと知った。
それこそ、コミュニケーションには問題のない子、つまり年齢から考えると幼いけれど、話せば伝わる子もいるし、まったく会話が成立しない子もいた。
こういうことを体感を通して知っていないと、「あの子はこんな子」と名前をつけた瞬間、その子のことが見えている気になるが、本当は見えなくなる、なんてことがあるのではないか。
括ってしまうと見えなくなるんだ。
そんなことを思っている。
結局、どんな名前をつけられようが、一人ひとりをその目で見て、その頭で考えて、関わっていくしかないのだよ。
でも、名前をつけられると、そういうことが疎かになりやすい。
名前をつけると対応の仕方が明確になる。
けれども、名前をつけると一人ひとりを見る視点が欠ける。
だからね、教育者の側が勝手な見立てで、「あの子はこんな子だ」って決めるのは、とても危険なことだと思う。
ただ、集団生活の中で生きにくさを感じているのであれば、手を差し伸べてあげたい。
わりと、そういう生きにくさって、集団の中だからこそ、浮き彫りになる。
パッと見でわかるものではないし、ちょっと話をしたぐらいで理解できるようなものでもない。
集団の中にいることで、「あれ、なんかこの子、ちょっと違った行動を取るよなぁ」といった感じで、発達の凸凹加減が浮き彫りになる。
凸凹加減を知るのは、手立てを考えるうえでとても参考になる。
でも、凸凹加減を知っただけでは何の役にも立たない。
昔、自分のクラスに、そういった診断を受けている子が何人かいた。
ある日の校内研修。
黒板の周りに掲示物が貼ってあると注意が散漫になって、なかなか授業に集中できない、という話を聞いた。
「それはいいことを聞いたぞ!」と、すぐに僕は教室に行き、黒板の周りにある掲示物をすべて剥がして、背面の掲示板に移設した。
もちろん背面の掲示板では収まらないので、廊下とか壁とか、いろんなものを使ったわけだけど。
確かに、全部剥がすとスッキリして、集中できる感じがした。
僕はわりと満足して、廊下を歩いて職員室に戻ったわけだけど、そんなことをやっているのは僕の教室だけだった。
ちょっとそれにビックリしたのを覚えている。
研修で聞いて、「あぁ、そうなんだ」と思ったら、すぐにやってみる。
効果が知りたいし、それで子どもたちの支援になるなら、お安いご用だ。
でも、実際に学んだことを実践する人って少ないんだな、と驚いた。
「先生、何してたんですか?」と職員室で尋ねられたので、教室の掲示物を移設していた話をしたら、周りの先生に驚かれた。
「だって、あなたのクラスにもそういう子、いるでしょ?」と尋ねると、「そうですね。でも、掲示物は前にも貼っておくものなので」みたいな返事が返ってきて、とてもガッカリした気持ちになったのを覚えている。
結局のところ、相手が朝顔だとわかっていても、支柱の差し方を知らない人、支柱を立てようとしない人の前で同じことなんだな。