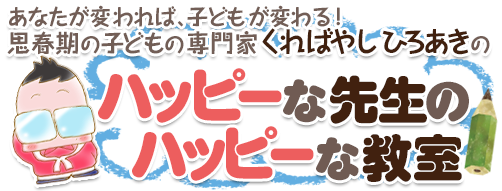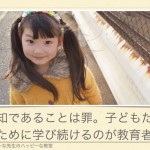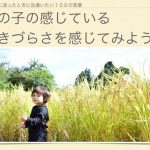僕らは本当に同じ世界を眺めているのだろうか?

みんな、「違う」ということ。
これをちゃんと認められる社会でありたい。
たとえば、好き嫌いがある子どもって多い。
大人だって多い。
偏食なんて呼ばれたりしてね。
でもさ、思うんだ。
僕とあなた、同じものを食べても同じ味がしているとは限らないんだな。
「へ〜〜っ。こんなに美味しいのに嫌いなの?」なんて笑わないで。
だって、同じ味がしてるわけじゃないんだもん。
たとえば、パクチーね。
あんなの、どう考えても「草」だよ。
「草」の味がする。
まあ、草、食べたことないけど。
でも、妻はパクチーを「美味しい」と言う。
最初はね、趣向の違いだと思った。
でも、そうじゃない。
たぶん、僕と妻では同じ食べ物でも同じ味がしているわけではないと思うのだ。
たぶん、これは、たぶんだけど。
僕が見ている赤信号と、あなたが見ている赤信号は別の色をしている。
何せ、僕はあなたになったことはないし、あなたは僕になったことがないから。
それはわからない。
聴こえ方だってそう。
僕の耳に聞こえている音と、あなたの耳に届く音はやぱり違う。
何が耳障りで、何が耳に心地よいか。
それだって異なるのだ。
昔、隣の教室の音が気になって仕方がない子どもがいた。
それは同じ教室にいる僕らには、まったく聞こえない音なのだ。
臭いだってそうだ。
香水の匂いを良い匂いと感じる人もいれば、臭くてたまらないという人もいる。
人は誰しも好きな香りと苦手な臭いがあるわけで。
それだって、たぶん嗅覚から届くものが異なるのだ。
僕らは人と接するとき、「異なる」ということを意識する必要がある。
「あなた」と「わたし」は違うのだ。
見えるもの、聞こえるもの、臭いも味も全部ぜんぶ。
僕らはみんな違うのだ。
同じだと思うからいらいらする。
なんで?って思う。
この人、おかしいんじゃない?って感じる。
でもね、異なるんだよ。
昔、情緒に障害を抱える子がいた。
相手の表情を見ても、その感情が読み取れないという。
特別支援学級のベテランの先生がこんなことを教えてくれた。
「あの子から見たら、みんな『千と千尋の神隠し』のカオナシみたいなものさ」
相手の表情を見て、相手の喜怒哀楽を察することができないのだ。
だって、この人にはそう見えているんだもん。
怒った顔も悲しんだ顔も、同じように見えているんだもん。
だから、生きづらさを感じてしまう。
怒っている相手を余計に怒らせてしまったり、悲しませてしまったり。
「察する」ために必要な要素がキャッチできないのだ。
あるお母さんの話だ。
子どもが泣いていた。
子どもが怒っていた。
それでも気づかずおしゃべりに夢中だった。
「わたしは夢中になると気づかない」と言う。
それで周囲を辟易させる。
そんなことってある?と思う。
我が子が泣き叫んでいるのだ。
大騒ぎしているのだ。
それに気づかない親なんているだろうか?
でもね、いるのかもしれない。
それはもう、その人にしかわからない感覚だから。
もしかしたら、子どものことが嫌で嫌で仕方がなくて無視をしていたのかもしれない。
もしかしたら、本当に耳に子どもの声が届かないのかもしれない。
もしかしたら、子どもの悲しい表情を見ても「のっぺらぼう」のように見えているのかもしれない。
これは、他人にはわからないことだ。
僕らは「自分」というフィルターでこの世界を眺めている。
「普通はこうだ」と考える。
でも、目の前の人のフィルターには、まったく別の世界が映し出されているのかもしれない。
そういう配慮を持って接すれば、世界はもっと優しくなると思うのだ。