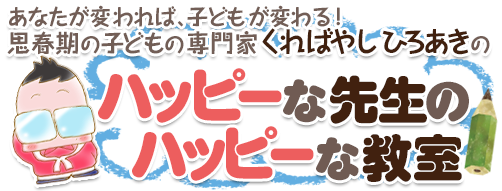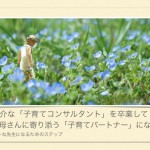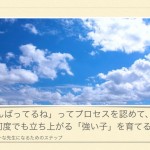なぜその校則があるのか、ちゃんと説明できますか?
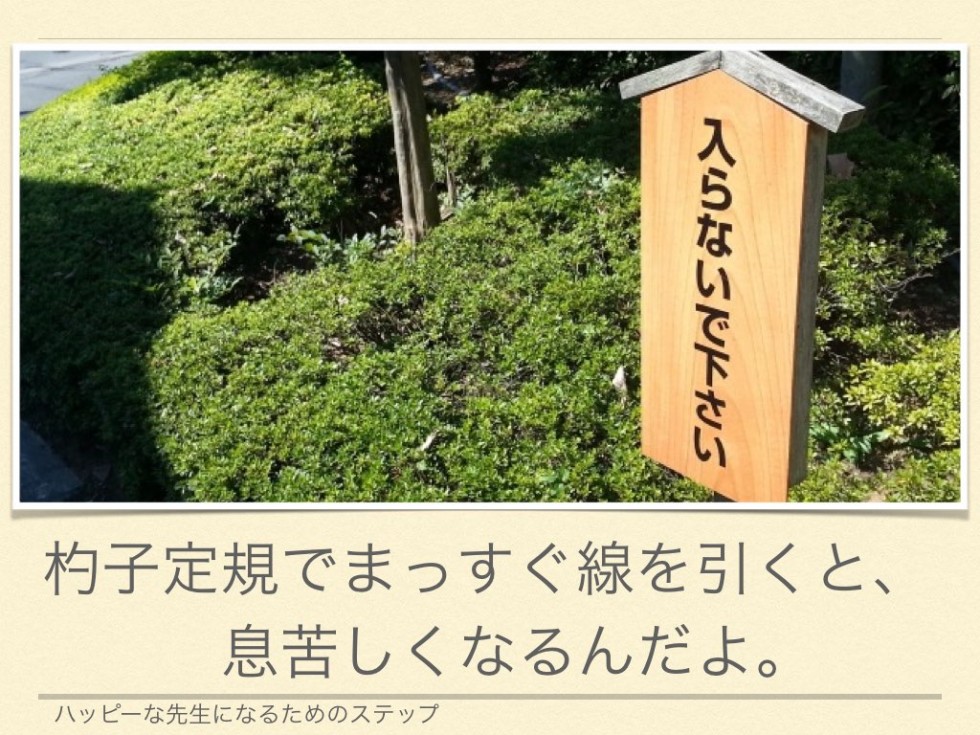
そのルール、本当に必要ですか?
学校にはどうでもいいようなルールがけっこうあったりします。
それらのルールは「子どもたちに愛され、保護者に応援される先生」を苦しめます。
子どもの気持ちに寄り添いたい。
けれど、ルールだから仕方がない…。
そんなジレンマの中で過ごしている先生もいらっしゃるでしょう。
だから、ルールなんか無視しろ!
…とは、言いません。
そんなことをすれば、学校は空中分解します。
うん!空中分解はよくないよね。
一つひとつの校則について、その校則がなぜあるのかきちんと理由を答えることができるでしょうか?
僕はずっと生徒指導の中心で仕事をしていました。
当然、「なんでこんなルールがあるんですか?」と、子どもからも保護者からも、それから若い先生からも尋ねられるポジションにいました。
正直言って、僕が作ったわけじゃないんだけどね…とは思いました。
けれど、そんな日々があったからこそ、一つひとつの校則と向き合うこともできました。
杓子定規にやってしまった方が楽なのはわかるけど…
「なんで、こんな校則があるの?」
そんな問いに対して、
「ルールだから」
「これまでこうしてきたから」
「学校はこういうものだから」
で、片付けてしまったら、子どもたちに愛されることも保護者に応援されることもありえません。
たとえば、こんなルール。
「学校に携帯電話を持ってこない」
おそらく、ほとんどの学校にあるルールなのではないかと思います。
若いころ、僕はこのルールがどうしても納得できませんでした。
保護者から下校時の安全のために持たせてほしいというような声があったのです。
しかし、学校の答えはNoでした。
それで、僕は先輩の先生たちに尋ねました。
「なんで、学校に携帯電話を持ってきてはいけないんですか?」
返ってきた答えはやはりこんなものでした。
「ルールだから」
「これまでこうしてきたから」
「学校はこういうものだから」
この答えはまったく答えになっていないと思うのです。
「職員室以外から外部に連絡が取れると、生徒指導上困るから」とも教えていただきました。
教師になって15年。
おもに、生徒指導に携わってまいりましたが、未だにそういう場面に出会っていないんですよね
いったい外部に連絡が取れると、どんな事件が起きるのでしょうか。
こんな話もあります。
ある雪の日、長靴を履いてきた子がいました。
先生は注意します。
「ウチの学校のルールでは、白い運動靴を履くことになっています。履き替えてきなさい」
髪の毛をしばるゴムは、紺か黒。その色は青だからダメ。
靴は真っ白。色のラインが入っていたらダメ。
どうやって説明するのだろう?
やはりこう答えるんだろうな。
「ルールだから」
「これまでこうしてきたから」
「学校はこういうものだから」
答えになってない答えを伝えることで、どんどん子どもたちの心、保護者の心は離れていきます。
校則を守らせることが目的になっていませんか?
どうでもいいルールを遵守しようとするあまり、学校と家庭のつながりが壊れていくとしたら、それは大きな過ちではないでしょうか。
「何のために」が大切。
守らせることは目的ではありません。
そのルールは何のためにあるのですか?
きっとルールの先にもっと大切なことがあるはずなんです。
「学校に携帯電話を持ってこない」
僕はこのルールを、こう子どもたちに伝えています。
「目の前に友だちがいるのに、携帯電話イジってたら悲しいよな。携帯電話がないと、コミニケーションが取れないなんて、悲しいと思うんだ。学校は集団から学ぶ場所。リアルに顔を合わせて、ぶつかりあって、一緒に泣いて、一緒に笑って、愛され方を学ぶ場所。僕はこの教室に携帯電話は不要だと思うんだけど、みんなはどうだい?」
もちろん、この想いは学級通信で保護者にも発信します。
「だから、携帯電話は学校にいらないんだぜ!」
そうやって胸を張って指導したい。
ちなみに、登下校が不安だという保護者にはこう伝えています。
「では、朝、職員室で僕に預けてくださいね。下校するときにお返しします」
大切にすべきことがわかっていれば、保護者のニーズにだって、ちゃんと応えてあげられるんです。
ハッピーな先生になるためのステップ
杓子定規でまっすぐ線を引くことが、正しいとは限らないんだぜ!