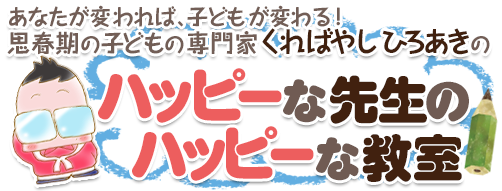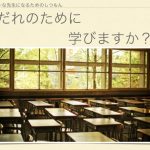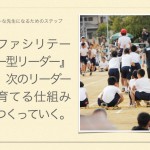コミュニティー型学級経営のススメ

「先生は絶対である」
そんな時代があった。
僕らの子どもの頃は、
先生は平気で体罰を振るったし、
「殴られたヤツが悪い」
という時代だった。
そんな時代だったから、
「管理する」という学級経営は成立していたのだと思う。
時代が変わり、
「学校の先生」の権威性は地に落ちた。
リスペクトの対象ではなく、
いつしか批判と不満のハケ口となった。
時代が変わり、
旧来の学級経営では学級を運営することが難しくなった。
指示を出し、指示に従わせる。
こういうやり方が難しくなったのだ。
情報が瞬く間に広がり、
多様な価値観が認められる現代社会。
「学校の先生」が人間関係のピラミッドの頂点に立ち、
支配していくようなやり方はもう時代遅れなのだ。
そういうやり方しか知らない先生が今、
苦しんでいる。
管理することでしか学級を運営してこなかった先生が今、
苦しんでいる。
そして、そんな教室で、
子どもたちもまた苦しんでいる。
これからの時代は、
コミュニティーの時代だ。
ピラミッド型の時代から、
互いが複雑に絡み合ったコミュニティーの時代なのだ。
僕はピラミッドの頂上に立つカリスマ先生ではなかった。
できるだけ、自分の存在を消そうと心がけた。
学級を運営するのは先生ではなく生徒だった。
僕じゃなければできないこと以外は、すべて生徒に委ねた。
一人ひとりにはコミュニティーの中での役割があった。
それは委員会や係など「「先生から割り当てられた仕事」ではない。
それぞれの存在そのものに意味があるということだ。
優しい子は優しく、たくましい子はたくましく。
穏やかな子は穏やかに、のんびりした子はのんびりと。
存在そのものが素晴らしく、ただそれが生かされるように心がけた。
「学校の先生」ができることなんて少ない。
僕はそんなに有能な先生ではない。
そんな自分を受け入れていたから、子どもたちには大いに助けてもらった。
生徒がいなければ、僕は何もできない。
だから、リスペクトと感謝を忘れなかった。
たぶん、多くの先生ががんばり過ぎている。
そして、疲弊している。
すべては「できない自分」を受け入れることから始まる。
そして、子どもたちに助けてもらう。
彼らは信じれば、その信に応えようとする。
教室はもはやカリスマを必要としていない。
だから、教室をコミュニティーにしてみよう。
ハッピーな先生になるための質問
できない自分はダメですか?
夏休み!学校や幼稚園、保育園の先生を無料ご招待!