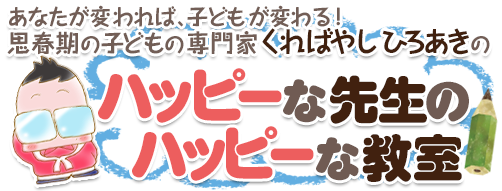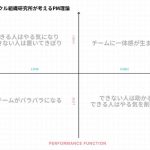川は上流から下流に流れるから、まず自分を律することから始めよう

「帝王学の教科書」である『貞観政要』の中に
「リーダーが信頼に足る人物じゃないのに、配下の者に真っ当なことを期待するのはどうよ?」
って話があってね。
面白いからシェアしておきます。
川は上流から下流に流れるもの。
組織も同じ。
上流が濁っているのに、下流の水が澄むのを望むのは、無理な話なのです。
以前ある先生がね、
「ウチのクラスは弛んでる!」
って怒ってたの。
忘れ物は多いし、チャイムが鳴っても生徒が戻ってこないのね。
で、教室で怒鳴っているのが、隣の教室で授業をしてくる僕の耳にも聞こえてくるわけですよ。
怒鳴って学級が良くなるなら、教育技術なんていらないわけですが。
怒るしかスベがなかったんでしょうな。
ウチのクラスの子たちまで、「隣、むっちゃ怒ってるね」なんてザワザワしちゃう。
困ったものよね。
それで次の時間、その学級に僕は授業に行きました。
「君たち、さっきは叱られてましたねぇ」なんて話す。
すると、子どもたちが訴えるのね。
「たしかにさ、俺らも悪いよ」
って言って、続けて
「だけどさ、ウチの担任だって授業に遅れてくるし、よく忘れ物するんだよ」
なんて言うの。
で、別の子が
「お前が言うな!って感じじゃない?」
と。
んで、生徒が笑う。
こういう状態、よくないよね。
担任の先生が信頼されていないのが伝わってきたな。
リーダーはさ、まず自分を律することからスタートしたい。
川は上流から下流に流れるもの。
上流が濁っているのに、下流の水が澄むのを望むのは、無理な話なのです。
あるコミュニティーのリーダーがね、みんなから全然信頼されてなくてね。
どんどんコミュニティーから人が抜けていったの。
そしたら、リーダーも怒るわけ。
「けしからん!」ってさ。
そんなとき、「みんなが悪い」って考えるか、自らの「在り方」を見直すかで、リーダーの器ってものが決まると思うのだよ。
自らが濁っているから、下流が澱む。
そのことを知っておく必要があるわけ。
自分を知り、自分を律し、それを形にして表現する。
そういうことができるかどうかなのよね。
僕は「忘れ物」とか「遅刻」とか、全然うるさく言わない先生だった。
「生徒指導の先生」のくせに、そこはうるさく言わないの。
「忘れ物」とか「遅刻」じゃ、学校は荒れないしね。
「荒れた学校の実情」を知っているだけに、僕の基準は「生徒にちゃんとさせる」よりも「子どもと良い関係をつくる」に比重を置いていたんだな。
「忘れ物」とか「遅刻」とかってさ、「人間だからそういうこともあるよね」って考えてた。
そんなことより大事なことが集団生活には山ほどあるんだよね。
で、子どもたちにはさ、「忘れ物」や「遅刻」をうるさく言わない代わりに「先生がミスっても責めるなよ」なんて笑って話してた。
その実、そういうミスはほとんどありませんでしたけど。
自らを律し、他者に寛容であれば、組織は自ずとあたたかくなります。
人の心をつかんで組織を動かすことは、実はそんなに難しくないんです。
どうでもいいことはどうでもいいとして、人としてそれはダメだろ?ってことについては厳しく指導する。
その辺のメリハリが大事だと思うよ。
厳しく接すれば、組織内にいる人たちもまた、他者に厳しく接します。
反対に、結局上流の水があたたかければ下流の水をあたたかいわけですわ。
面白いものです。
水は上流から下流に流れる。
ですから、まず上流の水がどんな状態か、よくよく吟味する必要があるのです。