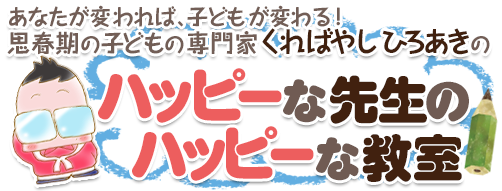人類は一人では子育てができない。

ワンオペ育児は人間らしくない子育てだ!
今、多くのお母さんが一人での子育て、いわゆる「ワンオペ育児」「孤育て」に苦しんでいます。
そこで、人間を「動物の1種である」という視点で、育児に目を向けていこうと思います。
チンパンジーは地球上で最も人間に近い生物といわれ、およそ700万年前に共通の祖先から枝分かれしたと考えられています。
チンパンジーの子育ては現代の子育てと似ています。
チンパンジーの母親は、なんと6年間つきっきりで子育てをします。
父親が子育てに参加することはありません。
母親は子どもを肌身離さず、つきっきりで子育てをするのです。
したがって、チンパンジーは6年に一度しか出産をしないのだそうです。
しかしながら、チンパンジーは孤独な子育てに苦しんだりはしません。
それではなぜ人間だけが孤独な子育てに苦しむのでしょうか。
その答えを知ると、「ワンオペ育児」がいかに人間らしくない子育てであるかがわかります。
人間ほどか弱い生き物はいない
生物という視点で見たとき、人間は毎年子どもを産むことができるようにできています。
少子化に悩む現代社会とは異なり、多産が当たり前の時代もありました。
ですから、多くの子孫を残し繁栄することできた、とも言えます。
これにも理由があります。
人類は大変か弱い動物です。
様々な「便利さ」を手に入れた現代人は、食物連鎖の頂点に君臨しているかのように振舞っています。
しかし、本来野生で生きてきた私たち人類は、他の動物のようなスタミナもスピードも腕力もありません。
木に登ることも、水中を素早く泳ぐこともできないか弱い生き物なのです。
現代人が自然の中に手ぶらでほっぽり出されれば、瞬く間に命を失うことでしょう。
私たちの存在が動物の世界ではか弱い存在であることは想像に難しくありません。
失われる命を想定して、多くの赤ちゃんが産めるように進化していったのです。
しかし、人間は成長の遅い生き物です。
他の哺乳類のように生後すぐに立ち歩いたりすることはありません。
ですから、長い年月をかけて育児をする必要がありました。
もしもお母さんが、チンパンジーのように一人で子育てをしなければならなかったらどうでしょうか。
毎年のように子どもを産むことはできません。
生物の営みと肉体はリンクしています。
そのようなミスマッチが起こるはずはありません。
チンパンジーは6年に一度しか赤ちゃんを産むことができない生物であり、人類は毎年赤ちゃんを産むことができる生物なのです。
ですから、それを可能にする育児方法があるはずなのです。
そして、それは生物として人類を見た場合、自然な育児であるとも言えます。
その育児方法が「共同養育」という方法です。
これこそが人間本来の子育てなのです。
自分の子と他人の子を区別することなく、みんなで育てていく。
乳の出ない母親がいれば、他の母親が乳を分け与えることもありました。
江戸時代の長屋文化のように、「みんなで育てる」という文化が日本にもあったわけです。
人間は大切な我が子を他人の手に委ねることができる唯一の生き物なのだそうです。
人間は社会性に富んだ生き物です。
その社会性を発達させたのは、この「共同育児」という育児方法と密接に関わっていることが理解できると思います。
私たちは社会性に富んでいなければ子育てができないようにデザインされているわけです。
出産に伴う孤独や不安感の正体
育児中にお母さんたちが感じる孤独や不安感は「産後うつ」の大きな原因ともなっています。
それは「女性ホルモンの変化」と関係があるようなのです。
出産が近づくと、通常の数百倍の女性ホルモンが体内を満たします。
これによって、お母さんに子を持つ喜びを感じさせるのだそうです。
それは、これから始まる大変な育児をがんばる準備をさせる仕組みだと考えられています。
ところがこの「女性ホルモン」は、出産と同時に急降下し一気に通常のレベルに戻ります。
すると、脳は孤独や不安を感じやすくさせるのだそうです。
この仕組みが「産後うつ」の大きな原因となっているのだそうです。
では、なぜあえて不安や孤独感を感じさせる仕組みになっているのでしょうか?
そこに人間らしい育児である共同養育につながるメカニズムが隠されているのです。
前述のように、人間の母親は出産を終えると不安や孤独を感じるようにできています。
すると、「誰かと一緒にいたい」「誰かと一緒に子育てがしたい」と自然に考えるようになります。
そして、社会性に富んだ私たちは自然とコミュニティーを形成していきます。
産後の孤独や不安感は、共同養育を支える仕組みとして、人間に備わった能力であると研究者は考えているのだそうです。
一人では子育てができないようにできている
私たち人間は、生き物の本能として、一人では子育てができないようにできているのです。
このことに、もっと向き合う必要があるでしょう。
子育てに孤独を感じているお母さんは全体の7割だという統計もあります。
先進国に比べ、極端に男性の育児参加が少ないのが日本の現状です。
6歳未満の子どものいる家庭の核家族率は8割にも上ります。
つまり、多くのお母さんが孤独な子育てを強いられている現状があるのです。
一説によれば、ママ友を作ろうとする「ママ友現象」は日本特有のものなのだそうです。
少子化対策として、保育所を増やしたり経済的な支援をすることが少し的外れな政策であることを感じていただけたでしょうか。
日本という国が本来もっていた子育ての機能。
これらがいつの間にか、失われてしまったのです。
このことにもっと目を向けてみたいと思います。
がんばらない子育てを実践する場
僕ら夫婦が主宰するプレシャスというコミュニティーでは、『親子de修学旅行』という企画を実施しています。
男子は僕の部屋でテレビゲームをしていたり、勝手に温泉に行ったり。
ジュースが飲みたいというので、僕がお金を渡して子どもたちがジュースを買ってきます。
悪い言い方をすればほったらかしです。
そして、そこに「ウチの子」と「ヨソの子」という視点はありません。
女の子たちは、ウチの娘を中心に女の子チームでうまくやっています。
その間、お母さんたちはお母さんたちの部屋でお酒を飲んでおしゃべりをしています。
困ったことがあれば大人のいる部屋に誰かが来ます。
それで子育てが成立しているのです。
一人っ子の子が、ここへ来るとお兄ちゃんもお姉ちゃんも妹も弟もいると喜ぶのだそうです。
それから、この春開催した『子育て万博』もそうでした。
子どもたちにもスタッフTシャツを着せ、トラブルがあれば近くの大人スタッフが対応しました。

母親が我が子につきっきり、なんてことはありません。
ですから、小さな子どもがいるお母さんも、気兼ねなくスタッフに加わることができたのです。
自分の子どもも他人の子どもも、区別なく面倒を見る。
そういった暗黙のルールがありました。
このルールは、現代社会では産み出しにくい時代になったのも事実です。
あるお母さんが口にした言葉が印象的でした。
「私が子育てをがんばらなきゃ!という思いが、ここへ来て手放せました」と。
共同養育こそが、本来の私たち人類が生き物として種を存続させ生命を維持するために培ってきた育児方法なのです。
ですから、これからはいかにしてコミュニティーを作るかという時代になっているのです。
グローバル化が叫ばれる昨今。
本当に求められているものはローカル化だと思うのです。
批判的な社会では、よりクローズドなものが重宝されるでしょう。
多種多様な価値観の中で、より価値観の近いもの同士がコミュニティーを形成していく時代がきています。
人間は一人では子育てができないようにできている。
そのことを忘れないでください。
子どもとつながる魔法の質問
だれと分かち合いますか?
【参考文献】
NHKスペシャル取材班
『ママたちが非常事態!?』
(ポプラ社)