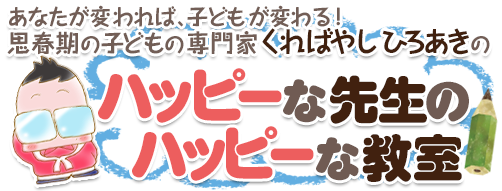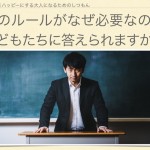校則が変わらない本当の理由

校則についての議論が後を尽きない。
学校の体たらく、
先生の感覚のズレ、
時代遅れ。
訳知り顔で、
そうおっしゃる専門家も多い。
だが、
本物の校則をちゃんと読んだことのある人は少ない。
マスメディアに「切り取られた一部」を見せられて、ジャッジをしていることがほとんどだ。
僕が知っている範囲で言えば、校則には「変更・新設」(←表現は異なるかもしれないが)するための条項があるはずだ。
それがないと、新設も変更もできないのだから、普通はどこの校則にでもある。
割と多いパターンは、「生徒議会(生徒会)などで審議し、その後生徒総会で可決し、職員会議で了承され、校長が認める」的な、まるで国会のようなクソ長い手続きが必要である。
学校が社会を学ぶ場所である以上、そういった手続きを踏むし、そういった手続きが必要だからこそ、理不尽なルールを新しく生みづらくなっている。
独裁政治を生み出さない社会の仕組みを学んでいるとも言える。
正当な手続きなしにルール変更などあり得ないのだ。
だって、ここは日本。
法治国家だもん。
そう、学校は教育機関であり、社会に出る準備を進める場所なのだ。
さて、僕は「生徒指導主事」という、いわば「校則」を守らせる側にいた人間である。
だが、できるだけ校則を軽くするように動いてきた人間でもある。
なぜならば、ルールが複雑なほど指導内容が増えるからである。
「前髪が眉毛にかかってはいけない」というルールがあるから、前髪が眉毛にかかることを指導をしなければならない。
そんなルールがなければ、前髪が床に届いていようが、指導しなくてもすむ。
ルールは少ないほど良い。
そんなわけで、生徒にはどんどん理不尽なルールを改めさせようとした。
ところが、である。
子どもたちは動こうとしない。
生徒会役員をやるのは、中2の後期や中3の前期である。
苦労して校則を変えたところで、その成果は自分たちの代で生かされる可能性は低い。
なにより、「なんで俺らがそんなに苦労して校則変えなきゃいかんのよ」という感じがある。
ルールは嫌だけど、苦労してまでルールを変えたいとは思わない。
誰かが変えてくれるなら変えてほしいけど、動くのは嫌だ。
そんなめんどくささがありありと伝わってきた。
ルールがあるのだから、正当なやり方でルールを変えようぜ、というのだが、全然乗ってこないのだ。
この空気感。
大人の空気と一緒だよ。
「日本の政治は間違ってるーーっ!」とか言うクセに選挙には行かない。
まして、立候補などしない。
文句は言うけど、我関せず。
対岸の火事。
「校則、おかしいっすよ!」っていう子どもたちに、「じゃあ生徒会動かして校則変えろよ」と言うと、「いや、めんどくさいっす」となる。
「日本、おかしいっすよ!」っていう大人に、「せめて選挙に行けよ」と言うと、「いや、めんどくさっす」となる。
あー、これが日本だよ。
文句は言うけど、動かない。
主張だけして、責任は取らない。
たまに、本気で動くやつがいて、
学校が変わる。
先生の働き方とかも、
本気で動く校長とかがいて変わる。
でも、あんまり本気のヤツっていない。
結局、この世界は本気のヤツが動かすのよ。
で、大抵のヤツは冷めてるのよ。
本気にゃなれないんだな。
なあ、本気になろうぜ。
校則がおかしい?
だったら変えようぜ!
それを学ぶのも学校だろ?
俺はそう思うんだ。