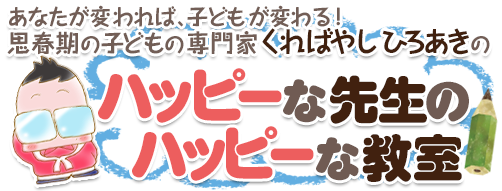学級編成に疑問を感じたときは
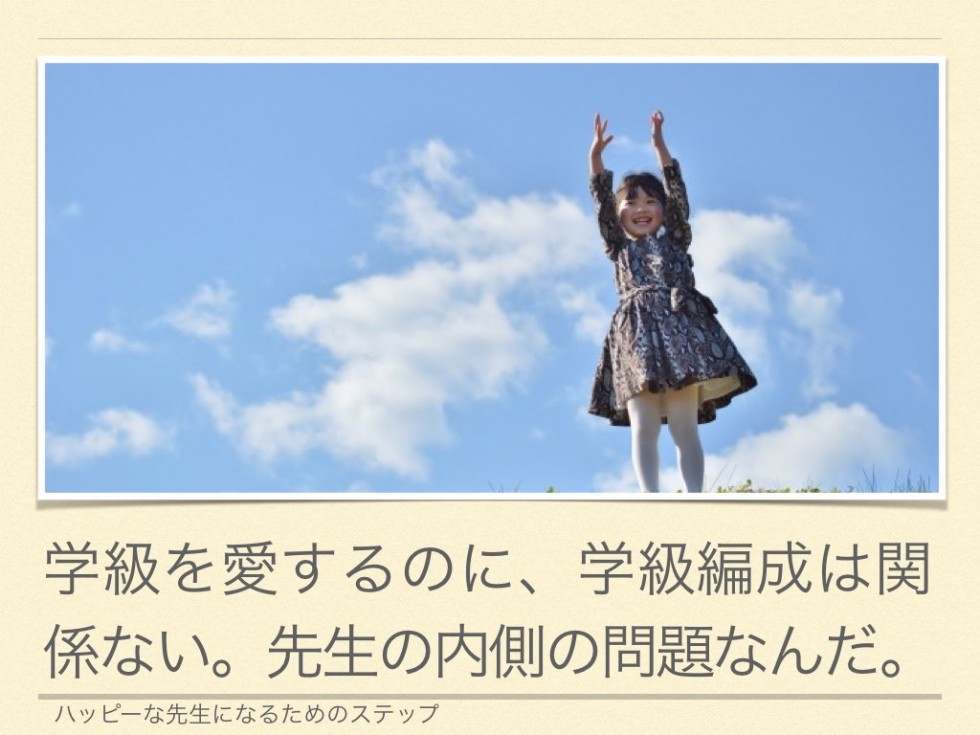
子どもが人のおもちゃをうらやむ理由
小さい子が、楽しそうに遊んでいるお友達のおもちゃを奪ってしまうことがあります。
我が子が小さいころ、よく地域の子育てセンターで遊ばせていました。
すると、ウチの子も知らない子を突き飛ばして、おもちゃを奪うんです。
そのたびに頭を下げて回りました。
ところが、奪ったらそのおもちゃで遊ぶのかというとそうではありません。
今度は別の子のおもちゃを奪ってしまうのです。
あれもほしい!
これもほしい!
全部ほしい、もっともっと欲しい♪
なんて欲張りなんだろう?
なんてわがままなんだろう?
と、そのときは思いました。
ところが、子どもというのは、おもちゃが欲しくてそんな行動をとるわけではないようなのです。
楽しそうに遊んでいる。
その時間、その姿を手に入れたくて、おもちゃを奪ってしまうのだそうです。
隣のクラスがよく見える。
自分の学級がうまくいかないとき、「学級編成が悪い」という先生がいます。
でもね、目の前の子どもたちをハッピーにしている先生は、毎年安定して「ハッピーな教室」を運営されています。
メンバー編成は関係なく、安定している。
この事実を受け止める必要があります。
かく言う僕も、学級がうまくいかないことがありました。
次から次に事件が起き、自分の学級ばかり生徒指導が入る。
異動になった直後のことでした。
「大変な学級をもたされたな」
そう感じました。
学級担任である僕がそんなふうに学級を見てしまったのですから、どんなクラスになったかは容易に想像がつくでしょう。
学級がうまくいかないことを子どもたちのせいにしてしまったら、学級担任はやるべきことが見えなくなります。
結局、個々の子どもたちには愛情をかけられましたが、最後の最後まで、僕はこの学級に愛着を感じられませんでした。
教室をハッピーにするために必要なこと
隣のクラスがよく見える、ということがあります。
しかし、忘れてはいけないこと。
それは、あなたがそのクラスの担任になったとしても、「同じクラスに育つとは限らない」、ということです。
きっと、他のメンバーだったとしても、あのころの僕のマインドではハッピーな教室はつくれなかったと思うのです。
逆に、今ならばまったく違う教室を生み出していることでしょう。
あの年、僕には深い後悔の念が残りました。
悩みました。
なぜ、このクラスを愛せなかったのだろう。
何度も何度も自問自答しました。
愛せなかったのは、子どもたちのせいではありませんでした。
愛は内側から生まれるものです。
愛を感じられなかったのは、僕の内側の問題だったのです。
そのことに気がついた翌年、僕はただただ目の前の子どもたちを愛することに専念しました。
すると、学級は明らかに変わりました。
いや、学級が変わったのではありませんね。
変わったのは僕自身。
その経験が「目の前の子どもたちをハッピーにする」というマインドを生み出しました。
学級を閉じるその日、あなたは、そして子どもたちは涙をこぼすことができるでしょうか。
悲しみに包まれるでしょうか。
学級に対する想いは、ちゃんと心が教えてくれます。
目を閉じて自分自身に問いかけてみてください。
「自分はすべてを出しきれただろうか?」と。
ハッピーな先生になるためのステップ
愛は内側から生まれるもの。心の底から愛してみよう。