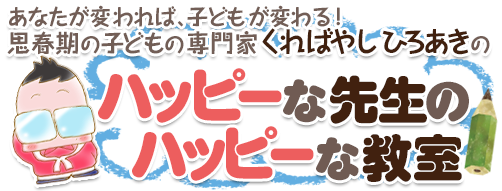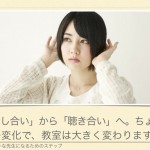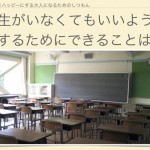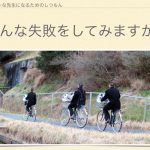たまには授業のことも書いてみよっと♪

教えない授業のススメ
授業中、
僕はほとんど教えません。
「教える」ということが、
僕の考えを押し付けているように
感じたからです。
以前、教育センターから
偉〜い先生がみえてね、
こんなことを言われました。
「先生自身がこの教材を
どう読んだのか伝えなさい」
僕は正直、
イヤだなって思ったんです。
この教材をどう読むか。
僕はこう読んだよ、
というのを伝えれば、
子どもたちはそれを正解だと
思ってしまうでしょう。
それが嫌なのです。
全力で話し合ってさ、
でも最後に「先生はこう読んだよ」
なんて言われたらさ、
話し合ってた内容が間違いだったみたいじゃない?
うん!
それが嫌なんだな。
ねえねえ、学んでるの?教わってるの?
子どもたちは、
一つの教材をいろんな角度から、
読みます。
それがおもしろいんです。
もちろん、
「誤った読み」
というのはあるでしょう。
僕はそんなとき、
こんな「しつもん」をします。
「ねえねえ、その根拠は?」
記述から離れないように
読んでいけばいいのです。
勝手な想像ではなくね。
どうして先生は
教えたがるのでしょうか?
それが子どもたちの
学ぶ意欲を削っているのでは?
と考えています。
幸いにも僕は、
国語という教科が、
大嫌いでした。
本を読むことも、
文章を書くことも、
好きだけど、
国語は嫌いでした。
嫌いだったからこそ、
これまで16年の間、
どうしたら国語がおもしろくなるか、
探求することができました。
もしも僕が国語が大好きな国語の先生だったら、
一生懸命教えていたんだろうな。
幸いにも大嫌いだったから。
まったく別の視点で
授業づくりができていると
思うのです。
先生の仕事は、
教えることではありません。
子どもたちに学びを届けることなんです。
これが授業者の志事だと考えています。
生涯に渡って学び続ける子
「教えること」と「学ばせること」には、
天と地ほどの差があります。
というか、
この2つはまったくの別物です。
僕は「学ばせること」の対極に
「教えること」が存在していると思うの。
「先生、
ここがわからないんですけど」
と尋ねられたとき、
多くの先生は熱心に教えてしまうでしょう。
だって、先生だもん。
そんなときこそ一歩立ち止まる。
こんな「しつもん」を投げかけるんです。
「どうしたら、
それがわかると思いますか?」
この瞬間、
子どもたちの学びは発動します。
ある子は、こう答えます。
「もう一度教科書を読み返してみます」
ある子は、こう答えます。
「◯◯くんならわかりそうです」
ある子は、こう答えます。
「辞書で調べます」
「んじゃ、がんばってね♡」
それでいいのです。
「先生、
こういうときは
どうしたらいいですか?」
「うん、
どうしたらいいと思う?」
はい、この繰り返しです。
困難にぶち当たったとき、
自分で解決していく能力を育てること。
それが、
生涯に渡って学び続ける子どもを
育てるんだな。
ちなみに、
どうしても行き詰まったときだけ、
ヒントを届けます。
では、
どんなヒントを届けるか。
「しつもん」と「ヒント」に、
教育技術の真髄が
隠されているように思うんだな。
ハッピーな子どもを育てる大人になるためのしつもん
子どもの瞳がキラキラ輝く授業って、どんな授業だった?
(「いいね」を押していただき「しつもん」の答えと一緒にシェアしていただけたら幸いです。)