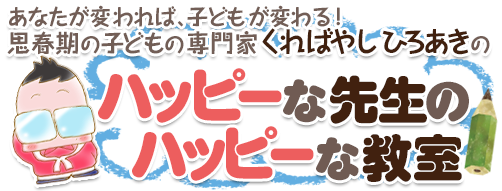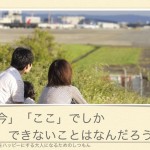この子が輝ける場所はどこですか?
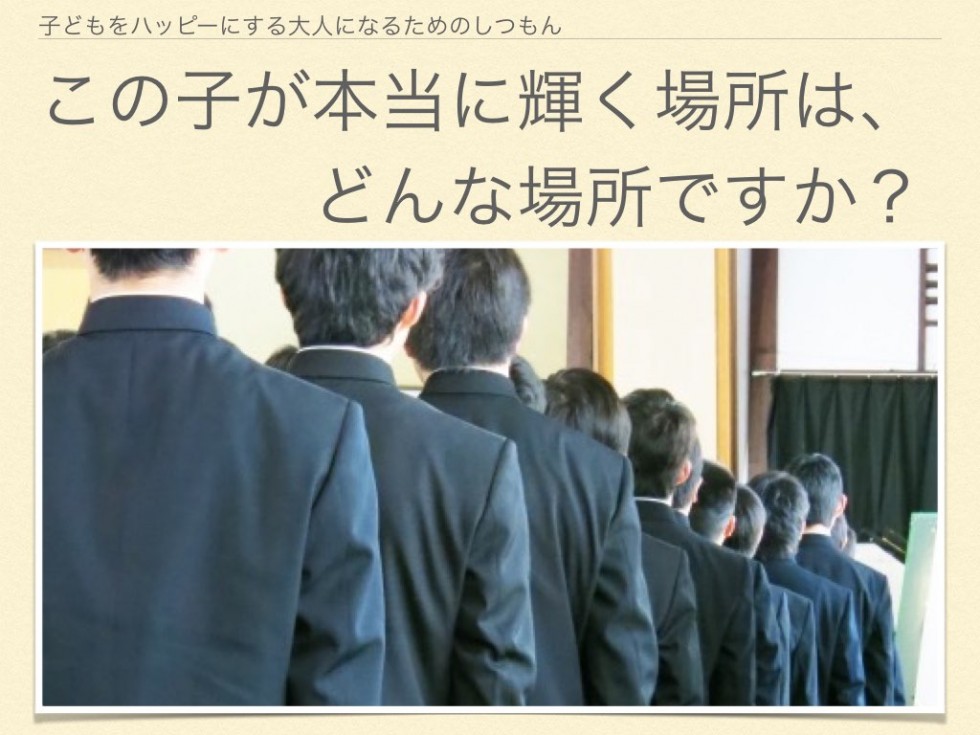
1年半ぶりの上海で、中国語が上達⁉︎
先日、1年半ぶりに上海へ行ってきました。
さまざまな職種の方をアテンドしての上海旅です。
中国は、ほぼ英語が使えません。
タクシーにしろ、飲食店にしろ、中国語が必要です。
ですから、日本から観光に行った場合、通訳なしでは食事することにも一苦労します。
で、今回は1年半ぶりの中国語。
で、実際に行ってみて感じたのは、
「あれっ?昔より上達してない?」
ってことでした。
自分は「できない」という思い込み
以前、上海で暮らしていたときには、僕よりも中国語が堪能な人がたくさんいました。
同僚の中には、中国語の検定試験に合格をしている人もたくさんいます。
現地で中国語を学んでいる人もいました。
ですから、マンションや警備スタッフの方と談笑されている方も見えました。
で、僕はと言うと、タクシーや飲食店で困らない程度の中国語しか話せません。
ほとんど聞き取れません。
ですから、自分の話す中国語に、自信はありませんでした。
ところがです。
1年半ぶりの中国。
当然、語学力は低下しているはず。
それなのに、なんだか上達している感じがしたのです。
どうしてそんなことが起こったのでしょうか。
頼られると、できる人の気分になるのだ!
今回のアテンドは、日本からのお客様です。
だれ一人、中国語が話せません。
どこに行くにも、何を注文するにも頼りにされます。
トイレを探すことも、メニューをもらうことも頼りにされます。
そう、以前の環境では中国語が下手だった僕。
でも、今回のアテンドでは最も語学力のある人になったのです。
そう!
語学力の問題ではないのです。
自分で、勝手に生み出していた「自分像」があったのですね。
できない自分。
できる自分。
それを作り出していたのも、自分でした。
こういうことは、子どもたちの世界でもあることではないでしょうか。
高いレベルでつぶれる子もいるのだよ
より高い環境に行けば、子どもたちの力は伸びると信じられています。
でも、本当にそうでしょうか。
そのように、育てられているでしょうか。
より高いレベルの学校を目指し、その結果その中で付いていくことができずにドロップアウトする子どもたちを見てきました。
たくさん見てきました。
一方で、「スベり止めの学校しか受からなかった」と涙を流した子がいました。
入学して数日。
「テストで一番になったよ」
「私、学級委員に選ばれたよ」
という報告をしに、うれしそうに顔を出してたんですね。
この子が本当の意味でキラキラ輝く環境。
そういうものを一緒になって探すことが大事なんです。
学校選びもそう。
習い事なんかもそうですね。
「より高いレベル」
「より有名」
それが必ずしも、その子を輝かせるとは限りません。
ハッピーな子どもを育てる大人になるためのしつもん
この子が本当に輝く場所は、どんな場所ですか?