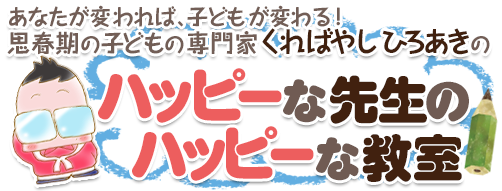子どもを愛することが難しいと感じたら

学校の勉強はよくできました。
偏差値の高い学校に入りました。
誰もがうらやむような人と結婚しました。
一見最善の人生を歩んできたように見えます。
それでも、子どもに虐待をしてしまう。
そんなケースもあるようです。
児童虐待をしてしまうお母さんもまた、その親から虐待を受けて育ってきた。
そんなケースをたくさん目の当たりにしてきました。
ですが、必ずしも虐待する親が虐待されてきた、とは限らないわけです。
しかし、彼女たちには共通点がありました。
それは、親に愛されてきた記憶、愛された実感がもてないという共通点です。
小さな頃から、親を喜ばせる役割を演じてきました。
親の期待に応えようと、一生懸命勉強しました。
そうして、偏差値の高い学校に入りました。
親の喜ぶ顔を見て自分も喜ぶ。
親の怒る顔が見たくなくて、そういう顔を見なくて済むように振る舞う。
そんな子ども時代を過ごしてきました。
本来、子どもの喜ぶ顔を見て親が喜ぶ。
子どもの悲しむ顔を見て子どもが悲しむ。
そういうものだと思うのです。
ですから、これは「あべこべの関係」です。
そんな幼少期を過ごしてきたのです。
親から愛された実感がないのです。
いざ、自分の子どもを目の前にしたとき、どう愛していいかわからなくなる。
それは仕方がないことなのかもしれません。
私たち人間は社会的存在です。
人との関係性の中で生きています。
赤ちゃんにとって、お母さんは唯一無二の存在です。
人の一生において、一番最初に培われる関係性が母子の関係です。
そこが、人間としての基礎となり、やがて社会性が育まれていきます。
人間の発達には順序があります。
社会に出れば社会性が育つわけではないのです。
多くの人に交われば社会性が育つわけではありません。
まず、たった一人の「だれか」との強い信頼関係が大切なのです。
育児は大変です。
でも、育児を放棄して自分のしたいことをすれば幸福になれるかというと、そうではありません。
他者を幸福にすることなく、自分を幸福にすることはできないのです。
それは、やはり私たちが社会的存在だからです。
愛されてきたからこそ、他者を愛する感情が芽生えます。
その愛情で人と関わるからこそ、人間関係は生まれ、私たちは幸福感を味わうことができます。
「自分さえ幸せならば良い」という考え方は、絶えず強い欲求不満の中で暮らすことになります。
これは幸せなことではありません。
幸せは「なるもの」ではありません。
幸せは「気づくもの」であり「味わうもの」です。
すでに「あるもの」。
ただ、それになかなか気がつけないだけなのです。
人間はいつだって「やり直し」ができる生き物です。
子どもとの信頼関係を築くのは、それに気づいた瞬間から始まります。
また、あなた自身が愛された経験に乏しいならば、今からだって遅くはないのです。
相手は誰だっていい。
基本的信頼を取り戻しましょう。
深めることです。
一人の人との関係性を深めることからスタートしましょう。
あなたに贈る魔法の質問
目の前の人を幸せにするためにできることは何だろう?
お母さんと、これからお母さんになる女性のための
オンライン・コミュニティー
にじのわ