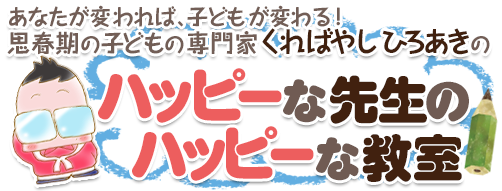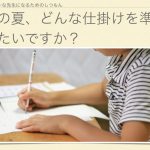部活動顧問を拒否することは『働き方改革』と呼べるのか?

意識高い系教師の皆様へ
ツイッターを眺めていたら、変形労働時間制が話題になっている。
んで、働き方改革が話題になっている。
ぼんやりツイッターを眺めながら思った。
「意識高い系教師」が多いな…と。
意識高い系…。
別に意識が高い教師だとは思わない。
あえてちょっと小馬鹿にして書いてるけどね。
意識高い系…。
なんか、部活動の顧問を拒否する的な投稿をやたら見かけた。
まあ、確かに勤務時間外の仕事だし、休日出勤だし。
気持ち、わからんでもない。
でもさ、僕は、この手の話を耳にするたび、不思議に思うのだ。
たぶん、あなたが断った仕事は、誰かが引き受けている。
「その人が断れないから悪い!」なんて言うなよ。
「断れない人」を悪にする論理は、「いじめられっ子にも非がある」って論理と一緒だからな。
3部かけもち
僕が最初に赴任した中学校は、全国コンクール常連の吹奏楽部があった。
休みなしで練習し、部員数も多く、楽器の準備室に教室丸ごと使っていた。
顧問の先生が転任すると、他校からやってきたのは合唱の先生だった。
そして、彼女は吹奏楽部の顧問を拒否した。
結局吹奏楽部を受け持つ先生はおらず、転任してきたばかりの新任の教務主任が受け持つことになった。
転任してきたばかりの教務主任。
しかも新任。
鬼のように忙しいことは想像できる。
だが、「私は部活の顧問はしない」と豪語した彼女は勤務時間を終えると、そそくさと帰宅した。
週明けにはしっかりとゴルフ焼けし、職員室で自分のスコアを喧伝していた。
吹奏楽部は…といえば、「もっとちゃんと指導してくれ」と保護者が怒鳴り込んできて、連日保護者会を開く状態だった。
音楽科の講師さんが加わるも、状況は変わらず。
なにせ前年度は全国コンクールまで行って金賞を受賞している。
全国で「金」。
卒業生の中には部活動での実績で公立推薦を勝ち取っている人が多くいた。
前の顧問もその触れ込みで部員を獲得していた。
勝手な話だけれど、保護者としてはなんとしても全国へ行かせたい!
が、しかし、それは無理な話だった。
結局、教務主任の先生は年度末に退職されてしまった。
そして、講師の先生も半年で本校を去ってしまった。
新入部員を取らなかった吹奏楽部は、3年生の部員12名となった。
当時、サッカー部の顧問だった僕は、校務分掌も「部活動」担当だった。
前年度顧問だった先生に、今年も「この部活でいいっすか?」と確認をし、新しく転任されてきた先生には「何部の顧問、したいっすか?」と尋ねてまわった。
たぶん、このあたりのルールは「全員顧問制」ではない地域独特のやり方だと思われる。
一応、部活動は仕事ではない…というスタンスだった。
まあ、趣味の延長…、そんなイメージ。
で、部活動の顧問がいないのが吹奏楽部。
そして、何をやっていたのか詳細不明の野外活動部だった。
吹奏楽部の部長さんの兄を、僕は担任していた。
そのつながりで保護者がやってきた。
「先生、なんとか最後まで部活動をやらせてあげてもらえませんでしょうか」
子どもたちも「先生、部活、やりたいです」と相談に来た。
「まあ、でも、俺、サッカー部の顧問だしさ」
そんな感じで断った。
保護者の思い、子どもの思い。
それを受け止めたけど、顧問の先生のなり手がいなかった。
んで、結局
「まあ、指導とかできないっすけどいいっすか?」
その確認だけはしっかりさせていただいて、顧問を引き受けることにした。
面白いことに、あとで野外活動部の保護者まで「くればやし先生、なんとか…」と懇願された(笑)
そんなわけで、僕はサッカー部・吹奏楽部・野外活動部の3部の顧問になった。
3部かけもち!
ちなみに、その年は隔週で夜間中学校の講師をし、研究発表で全国大会に行き、研究論文は入賞し、組合活動では支部の青年部長をさせていただいた。
んで、3部かけもち!
まあ、圧倒的なスピードで仕事するから、問題はないんだけど。
さすがに定時では帰れなかった。
初任の学校だしね。
それで話を元に戻そう。
みんなで動くから働き方改革だと思う
部活動を拒否することは『働き方改革』ではない。
みんなで話し合って練習時間を縮小の方向に持っていったり、休日の練習を見直したりすることが『改革』ではないだろうか。
みんなを巻き込んで議論を進める。
これが大事だと思うんだ。
「全体が動かないから、まず個人から」ってやり方はさ、お前はいいかもしれないけど、他の人がそれを被ることになるだけなんだ。
「被る人間が悪い」なんて言うなよ。
それ、いじめっ子の論理と一緒だからな(←2回目)
初任の頃からずっと、「校務分掌に軽重がありすぎる」と訴え続けてきた。
校務分掌表のあらゆる仕事に名前が載っている僕。
一方で何もない先生もいた。
管理職が言う。
「あの人に任せても仕事できないから…」
結局できる先生にしわ寄せが行く。
校内における仕事の総量が変わらない以上、「学校の先生」の仕事はゼロサムゲームである。
FXと同じ。
だれかが得をすると、だれかが損をする。
総量は変わらないのだから、そういうことになる。
だれかが断った仕事は、だれかが引き受ける。
「使えない先生」がいると、そのしわ寄せは「使える先生」が引き受けることになる。
仕事の総量を減らす努力をせず、仕事を拒否し、自分だけ「働き方改革」を行うことは、結局他者から見て「わがまま」に見えてしまうのだよ。
だから、意識高い系の先生の意識の低さに辟易している。
仕事を拒否することが働き方改革だろうか?
本当にそうだろうか?
圧倒的な仕事量を圧倒的なスピードでこなしてきた僕には、その薄っぺらさが気に入らないのだ。
まあ、俺には関係のない話だけどね(笑)